『マリ・ラウれぽうと』
#01『『おやすみなさい、ぼくの、マリー・ルウ』によせて』
月明
・・・ナゾルコトカナワネ キミノ ナ・・・
なぜこの言葉が浮かんだのか、わからない。
劇の稽古場を覗かせていただいた時、彼らは台本を持っての発声練習をしていた。普段着に身を包み、蛍光灯の明かりの元、真白き台本を手にした「目に映る彼ら」はまだ、道行く人のそれとさして変わりはなかった。
声、そう、それは声。。。 ひとりひとりの声は時間を追うごとに混ざり、溶け合い、ひとつの流れを生んだ。滔滔と流れる音の波。。 高く低く、空気を震わし、進む。。。
それは台本を離れ、物語を越え、視覚や聴覚が意味をなさなくなったその時、深き深き青の底で耳に聞こえぬ音となった。音は言った。。
・・・ナゾルコトカナワネ キミノ ナ・・・
そう、それは、日疋士郎がこの作品に隠しこんだ、言葉の先にあるメッセージのひとつだったのだろう。夢と現実との狭間において、ふと垣間見る、忘れたはずの記憶に似て。。。
日疋さんの世界は、どこか異次元的であり、異空間的である。言葉を巧みに操り、ひとつの確固たる物語を紡ぎだしながらも、そこから織り上げる作品は、演じ手によって如何様にでも変化するであろう弱竹のごとき嫋やかさを併せ持つ。実際に耳にしたのは、『おやすみなさい、ぼくの、マリー・ルウ』の台本冒頭のほんの一部であったにもかかわらず、その世界観は、広がる時空の深さ、面白さを十分に感じさせてくれた。果たして、楽日の舞台は想像していた以上のものであった。
赤きサカナを作品の軸としながらも、広がるのは青く暗い世界。まるでどこかに光を置き忘れてきたかのような、影ばかりが強調される深い空間。物事に表と裏があるのなら、その裏側にのみ焦点を中てつづけたまま、粛粛と進む物語。過去と現在とが繰り返し交錯し、やがてベクトルは幽かな未来を暗示させる。。。 この虚無的なまでの音と色との世界において、地と図とを意識することはいつしか意味を失い、結ばれる「像」が視覚を越えたとしても、届けられる「声」が聴覚を越えたとしても、なんら不思議はないように思われた。。。
作品を今ここで思い返すのはまるで、若い劇団の織り上げた色鮮やかな反物にそっと頬寄せているようでさえある。今はまだ粗いその織目が、巧緻な模様を描くときが楽しみである。

(C) Kazuyuki Matsumoto
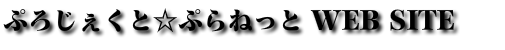
 HOME
HOME
 れぽ〜と
れぽ〜と